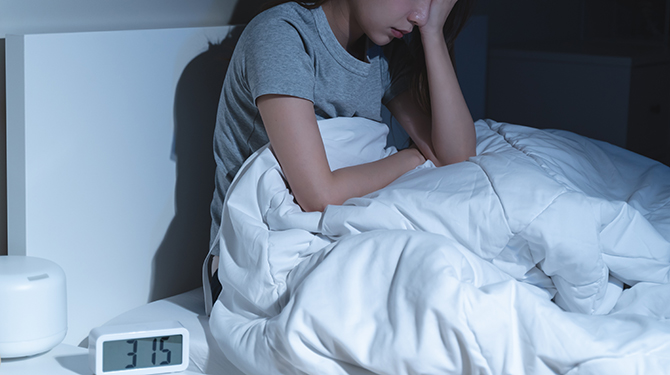※この体験談は、執筆者の先生ご自身の思いや感情を、できる限りそのまま表現いただき、私たちもそれを尊重いたしております。表現、用語などは誤解のないように配慮いただいておりますが、お気づきの点がありましたらご意見いただければ幸いです。
私は医学部時代から付き合っていた同級生と初期研修2年目の時に結婚をしました。私自身は医学部に学士編入で入っておりましたので、結婚時点で自分は29歳、相手は27歳でした。この時点では「せっかく医学部に編入をし、医学の勉強をして、医師免許が取得できたのだから医師として活躍したい」という気持ちがあり、長期的にはバリバリ働きたいと思っていましたが、「子どもを育てたい」という漠然とした夢も捨てきれずにいました。
自分の体力、不妊リスクを考え、35歳までには子どもを産み終えたいと思っていました。初期研修の間は小児科や脳神経内科に進むことを考えていましたが、子どもを育てながら土日の病棟業務や夜間の当直業務を続けることは難しいかもしれないと思い、自分が大好きな外来や訪問診療をメインでできる総合診療/家庭医療のプログラムに進むことにしました。
初期研修2年目に排卵誘発を経て妊娠し、専攻医1年目の秋に出産をしました。産休は規定の産前6週から取得し、予定日ぴったりに2600g台の男の子を出産しました。育休は1年間取得しました。
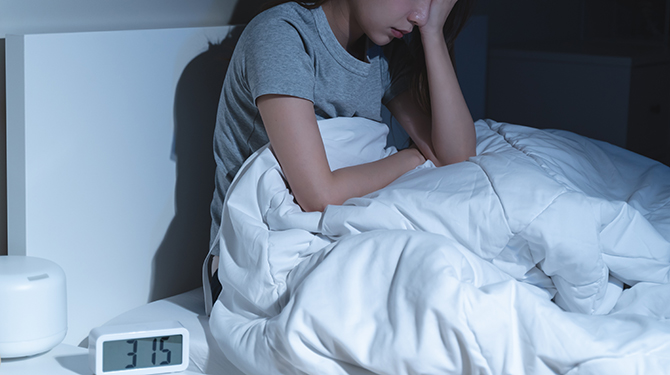
育休中は夜間の頻回授乳で悩みました。子どもの哺乳瓶拒否もあり、母乳メインで、ミルクはあまり使いませんでした。子どもが生後半年になるまでは夜間に4-5回、1歳半になるまでは夜間2-3回起こされ、授乳をしていました。今振り返ると、当時は睡眠不足で心も体もすり減っていました。
加えて子どもは2600g台と低めの体重で生まれ、生後半年以降は体重増加不良で、体重曲線から少しずつ外れるようになりました。かかりつけの小児科は母乳外来を設けていたので2-3週間に1回受診をしました。受診は元助産師さんに自分の悩みを聞いてもらえる癒しの時間でしたが、「どうにかせねば」という焦りが常にありました。
また自分の睡眠不足と元気いっぱいの子どもの世話で、家事は思うようにできず、「妻としても母としても医師としても自分は不十分なのではないか」と思うことがよくありました。特に自分の場合は実両親も義両親も県外にいたので孤独感もありました。
その中で自分の救いになったのはこども支援センター(いわゆる児童館) での時間です。最初は「自分は医師なんだからしっかりした自分を見せなきゃ」と謎の義務感を抱くこともありましたが、そこで出会った他のお母さんお父さんたちとの悩みの共有の場はとても有り難かったです。また県外にいる実両親とも毎日ビデオ通話をするようになり、子どもの成長を見てもらうと同時に、自分の悩みを吐き出すようにしました。
一方で夫や周りの専攻医はキャリア面で前進しているのに対して「自分は足踏みをしている」「本当に職場復帰をして、キャリアを続けられるのだろうか」と不安に思う日々がありました。時には夜間に泣き出し、夫に対して「自分は子どもの世話と家事で日々が過ぎ去る一方で、あなたには楽しく話せる同僚がいて、仕事とキャリアもあって羨ましい」「自分は子ども以外の誰の役にも立っていない」「生きている意味が分からない」と乱暴な言葉を投げつけることもありました。その度に真正面から向き合ってくれて、自分の気持ちに寄り添ってくれた夫に感謝をしています。
子どもは1歳時点で第5志望の保育園に途中入園できることが決まりました。保育園は自宅から車で10分と少し遠く、入園させるかどうか悩みました。また入園が年度途中に急遽決まったので上司に (その可能性について事前にお知らせはしていたものの) 「1ヶ月後に研修再開したいのですが可能でしょうか」と無理なお願いをせざるを得ず、申し訳ない気持ちになりました。
最後まで悩みましたが夫や両親、周りの子育て中の友人5-6人に相談し、最終的には1歳時点で入園させることを決めました。初めて子どもを保育園に預けたときは子どもから離れる寂しさと復帰後の生活に対する不安で泣きそうでした。
働き方については上司の配慮があり、自宅近くの総合病院に時短勤務する形で復帰をさせていただきました。復帰後も夜間に授乳をしていたので睡眠不足はありましたが、久しぶりの臨床でとても新鮮な気分でした。患者さんの診療もそれまでの臨床の中で一番やりがいを感じ、働けることに対して幸せを噛みしめる日々でした。
その後、卒乳をする1歳半までの間は保育園をほとんど休むことなく元気に通ってくれました。頻繁に休むようになったのは1歳半以降で、特に4-6月頃は手足口病やアデノウイルス感染症で2週間に1回、3-4日連続で休むということが頻回にありました。自分の場合は実両親も義両親も県外にいたので、自分と夫で交互に休みを取得しました。外来日だけは自分が休まないよう夫に協力をしてもらいました。病児保育には申し込んでいましたが、使用条件が厳しく (前日に診断書が必要、手足口病など特定の感染症では使えないなど)、使う機会がありませんでした。
自分は周りの目を気にしてしまう性格なので、仕事を急遽休む際、上司や同僚に連絡を入れる時に深い罪悪感を抱きました。具体的には専攻医の身分で休むこと、患者さんよりも自分のこと (自分の家族) を優先していることに対する罪悪感でした。
また各科の研修で週1回、20時頃までカンファレンスをしている科があったのですが、そういった場に参加できないことに対しても罪悪感がありました。周りにどう思われているか不安でした。その一方で、18時までに子どもを保育園に迎えに行き、19時までにご飯を作り、食べさせ、遊び相手をし、20〜21時までにお風呂に入れて寝かしつけるという毎晩のルーチンは1, 2歳の子どもにとっては重要だと考えていたので、そちらを優先させていただきました。

上記、自分が抱えた悩みや葛藤について沢山書いてしまいましたが、自分自身は (専攻医/男性医師の育休取得実績が沢山ある) 理解のある環境で働けており、感謝の気持ちしかありません。また「子育ての経験は医師/家庭医としてプラスでしかないから自信をもって」という周りからの温かい声かけに日々心が救われています。
育休中、そして職場復帰後は医師向けのコーチングを定期的に受けながら自分の罪悪感や固定観念を整理してきました。また自分と同じように悩む医師たちの声を形にしたいと思い、「医師の妊娠/出産/子育て/キャリア体験記」を集めたサイトである「ぽれり」を立ち上げました。
これらの活動を通して学んだのは、人生計画が重要であること、そして一度きりの人生なので周りの目を気にしすぎず、自分のやりたいこと、なりたい自分を大事にして良いということです。周りを頼ったり、(産後ケアや家事代行を含む) 外部のサービスも積極的に利用して良いと考えています。
私自身、悩みは尽きませんが、子どもは宝なので、悩みながらも日々の幸せを噛み締めていきたいです。